読書について、最近の僕が思うこと
読書はしたほうがいい。読書をすれば教養が身につく。想像力や豊かな心を育むことができる。最近の若者は読書しない、云々。そういった物言いを耳にしたことがない人はいないだろう。しかし、読書をめぐる世間一般の言説については、自分にとってどうしようもなく違和感があるというか、どうにも腑に落ちないことだらけである。この文章ではどうしてそう感じるのか自分なりに考えてみる。
小説、随筆、詩、戯曲、漫画、絵本、新書、学術書などなど、一口に本と言っても、じつにいろんな種類がある。その中で、僕ははっきり自分の意志で読む本を選ぶようになった中学時代から小説というジャンルに一番魅了されてきた。それもエンタメではなく純文学にだ。きっかけは朝読書。僕が通っていた中学校では、毎朝10分読書をする時間が設けてあって、それで何か本を持ってこないといけないから、芥川龍之介の『蜘蛛の糸・杜子春』(新潮文庫)を書店で手に入れた。
小学生の頃、NHKの番組だったと思うが、「杜子春」を子供向けにしたアニメみたいなやつを観ていてそれが妙に印象に残っていたこと、芥川賞というよく名前を聞くけれど何のことかさっぱり分からない賞があることなどが理由だったが、実際はただ単に薄くて読みやすそうだったからというのが本当のところだ。僕は小さい頃から本が好きだった。幼稚園でも周囲の子たちと遊ぶのではなく、本が置いてあるスペースでいつも一人で絵本を眺めていた。小学校に入ってもまあまあ本は読んだが、大半は漫画を読み、ゲームをして過ごしていたように思う。そんなわけで、文字だけで書かれた本格的な小説にふれたのは中学校に入ってからだったが、それはまさに僕にとって初めて大人への道に足を踏み入れるような経験だった。
それから僕は父の本棚から勝手に小説を取っていって読み漁るようになった。カフカの『変身』、サガンの『悲しみよこんにちは』、ヘッセの『車輪の下』、遠藤周作、川端康成、阿部公房、村上春樹の一連の作品…… そういうものに加えて、当時流行っていた宮部みゆきや東野圭吾なども中学生らしくそれなりに面白く読んだ記憶がある。そういう経験を通して、小説というものは漫画やゲームと同じくらい面白い、いやひょっとしたらそれ以上に面白いんじゃないかなと思うようになった。それが12歳から15歳の頃。あの頃の自分はまさにスポンジだった。手に取る本の一冊いっさつがまさにアイ・オープナーであり、まぎれもなくエキサイティングなものであり、そこに書いてあることの一つひとつが現実であろうとなかろうと関係なく、体に吸収されていった。
高校時代は洋楽に熱中していて、ほとんど本は読まなかった。再び自分のなかで読書熱が再燃するのは大学に入ってからである。この時期の自分は図書館が一番の友だちだった。人間の友だちもいるにはいたが、しょせんネクラな洋楽オタクだったので、片手におさまるほどだった。特に思い出深いのは柴田元幸の翻訳。ポール・オースター、スティーヴン・ミルハウザー、スチュアート・ダイベック。正確無比なその翻訳は、クラシック音楽でいえばマウリツィオ・ポリーニのピアノといったところだろう。
英米文学を中心に、ロシア文学、フランス文学、ドイツ文学、イタリア文学、東欧文学など、とにかくかたっぱしから読み漁った。『カラマーゾフの兄弟』も『アンナ・カレーニナ』も『ボヴァリー夫人』も『パルムの僧院』も『魔の山』も、みんな読んだ(『カラマーゾフ』については、中3のときに買ったもののまったく読めなくて挫折し、大学4年になってようやく読破したという、はなたれ小僧エピソードがついている)。何かの文章でポール・オースターが書いていたと思うが、この当時の僕はほとんどそれと同じように本によって新しい考えがばんばん輸血されていて、四六時中ほとんどわけがわからない空想めいた考えで頭がいっぱいになっていた。深夜まで本を読むせいで日中には青白い顔をしてふらふらしていた。
……というのが、青春時代の終わりに至るまでの僕の読書遍歴のすべてである。はっきり言ってしまうと、僕は読書の効用という考えにほとんど嫌悪感に近いものを抱いているのだが、その理由はもう、こういう読書歴を恥ずかしげもなく披歴しまえば明らかだろうと思うのである。生来、僕は物語というものに惹きつけられるたちで、何かの目的のために本を手に取ることがほとんどなかった。今ではどちらかというと物語よりも新書やノンフィクションを読むことが多くなったが、それは僕が社会人として働くようになり、「効用」というものを意識せねばならない程度には社会化されたからだろう。ほとんど無限の時間が自分の手の中にあって、好きな本を好きなだけ読んで過ごしていいという天国は永久に失われてしまった。大人になるというのはそういうことだ。
学生の頃、人生における大事なことの半分くらいは書物から学べると僕は思っていた。こんなブッキシュかつナイーヴな考えは、今では鼻で笑うしかない。しかし、そう言いながらも、あの頃の青臭い考えを捨てたくない自分がいるのもまた確かなことだ。大人たち、とりわけ学校の先生たちが本を読みましょうなどというのが不思議というか、なぜそんなことを言うのかがわからなかった。総じて、本は自分にとってよどんだ空気で息が詰まりそうな青春時代を生きのびるための新鮮な空気だった。だから、本を読めば語彙が増えるとか、他者に対する想像力を養うことができるとか、まあ部分的には確かにそうなのだろうけど、そういった考えはどうしても自分にはピンとこないのである。わざわざ空気を吸うことの効用を説明されたところで、それが何か心に響くだろうか。僕の世代はすでに知らないことがあれば人に訊くのではなく、図書館に行くのではなく、インターネットで調べるのがすでに当たり前だったのもあって、なおさら何か知識を求めて本を読むことはあまりなかった。いまでは、そういう考えがいかに愚かしいことなのか分かるようにはなったつもりだが。
結局のところ、読書は何かをもたらすこともあれば、純粋に時間の浪費、ひどければ精神的な害悪になることもあって、それは個人によってさまざまであるということを考えれば、僕は手放しに読書がすばらしいなどと言うことは無責任なのではないかと思う。読書をしたほうが豊かな人生を送れる。多少はそうかもしれない。少なくとも読書量ゼロよりかは。しかし、『恋愛の技法(アルス・アマトリア)』や『恋愛論』や『高慢と偏見』を読んで恋愛や結婚に対する考えを深めたとしても、何かしら行動を起こさない限りその人が現実的に恋愛を経験し伴侶を得る可能性はかぎりなくゼロに近そうだ。
当たり前の話だが、人は読書をしているときは、それ以外の行動をとらない。ということは、読書に時間をかければかけるほど、その分だけその人は自分の頭で考えたり行動したりする機会を失うということである。もちろん、何も読まずに考える人は薄っぺらい。しかし、あまりに読みすぎた人も同じく凡庸な発想しかできないというのはよくあることだ。最近、市川沙央の『ハンチバック』によって読書という行為そのものの特権性ということが注目されるようになってきたが、さまざまな理由からそもそも物理的に読書が困難な人たちはどうなるのか。読書がどう作用するかは個人によって違う。僕の場合は空想の世界に遊びすぎるあまり、いい意味でも悪い意味でもバランスというものがまったく欠けた若者になってしまった。
しかし人は変わるものでもある。最近の僕は、もっぱら読書量を稼ぐことよりもいかに質の高い読書ができるかということの方に関心をもつようになった。20代半ばくらいまでは旺盛な食欲を満たすようにして、やたらめったら読書するということを繰り返していた。しかし日々の雑事に追われ、感性というものが磨滅していく一方の今の自分には、とにかく量よりも質だ。時間はなくなった代わりに収入源はできたから、気にいった漫画なんかは全巻大人買いしたりもする。ひょっとしたら、僕は10代~20代なかばの読書にひたすら夢中になれていた頃の気持ちを思い出させてくれる体験を求めているのかもしれない。そういう意味では、昔ほど「文学」でなければだめだという変なこだわりは薄くなってきた。
若者の読書離れという表現は、大衆に読書が浸透するようになってから洋の東西を問わず、繰り返し言われてきたことのように思う。今も昔も、若者は本を読まないのだ。いつの時代も、若者は読書にだけ関わっていられるほど暇ではないし、若気の至りというか馬鹿の勲章というか、そういうものの数を増やすのに余念がない。そして、年をとってから「若い時分にもっと本を読んで勉強しとったらよかったんですけどね、ははは」などと言い出す(そういう人に限って、その後の人生でコンスタントに本を読むようになる可能性は低い。夏目漱石が友人の忠告を無視して建築家になっていたとか、あるいは村上春樹がこれから歴史小説を書いてノーベル文学賞ではなく吉川英治文学賞をとる並みに低い)。これはたぶん、紙の本が廃れて電子書籍や朗読を聞くのが圧倒的多数の時代になっても、寸分たがわず繰り返されるだろう。ただ、世の中の圧倒的少数に位置している若者たちは、何も言われなくても本を、それも19世紀の長大な小説を好んで読むだろう。自らの読書歴をふりかえると、僕はそういう若者たちには共感せざるを得ない。
とはいえ、読書で一番大事なことは、なるべく自発的に、自分の感性で選び取った本を読むことだろうと思う。べつに古典小説を読むほうが漫画やラノベを読むより偉いなんてことはない。もし世の中の人たちがみんな『戦争と平和』やら『レ・ミセラブル』やらを読むようになったら、今度はこの作家のこの作品を読んでいるほうがより高尚である、みたいな感じでどんどん知的なヒエラルキーが強化されていくだろう。きりがない。文学はみずからの教養をひけらかし、競争や対立をあおるものでは決してないはずだ。ある意味、教養を得るために読書をしましょうという言説に対して無関心でいられる人、読まなくてはならぬというキャノンではなくて無名の作家の無名の作品でも自分が面白いと思うから好きなんだとはっきり言える人のほうが健全なのかもしれない(これは自戒の念を込めてもいるのだが……いやはや)。まあ、日常的には、人に勧められた本がつまらなかったときはひどく気が滅入ったり腹が立ったりするものだが、自分で選んだ本であればつまらなかったとしても仕方がないとあきらめがつく、という程度の教訓である。

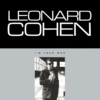



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません